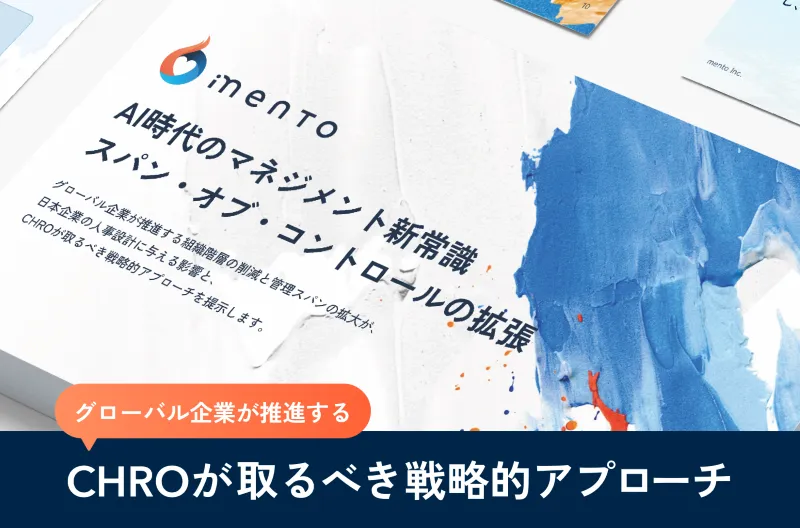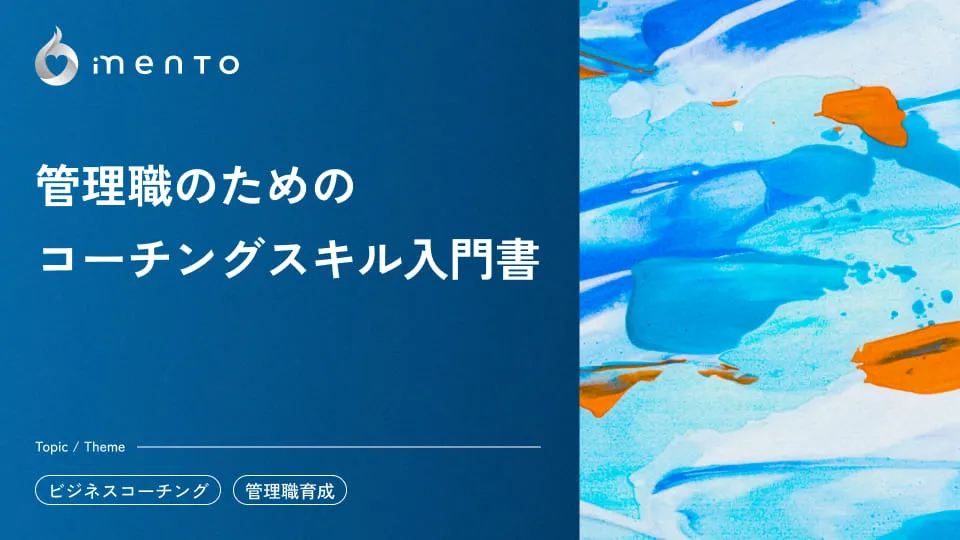


【コーチ監修】管理職のためのコーチングスキル入門書
著者:株式会社mento コーチサクセス/HR 鈴木 麻理子
2021年よりmento登録コーチとして活動を開始。2022年にmentoへ入社し、コーチサクセスとして約200名の登録コーチのサクセス・サポートを担いつつ、企業のミドルマネジメント層をメインにコーチングを提供。有償セッション経験時間は850時間超。(一財)生涯学習開発財団認定プロフェッショナルコーチ資格保有
INDEX
「短期的な成果だけでなく、長く育つチームをつくりたい」「世代や価値観の違いを前に、どう接すればいいか迷う」「1on1や会議でも、なかなか本音の対話が生まれない」。変化の激しい今、多くの管理職がこうした“関係性のマネジメント”に課題を感じています。
今、管理職に求められているのは「指示する力」ではなく「引き出す力」。その手段として注目されている「コーチングスキルを活用したマネジメント」は、部下との信頼関係を築き、主体性を引き出し、成果へつなげるスキルとして、多くの企業で導入が進んでいます。
本記事では、「コーチング型マネジメントとは何か?」という基本から、すぐに実践できるスキルや導入事例までをわかりやすく解説します。「チームの力をもっと引き出したい」と考える管理職の皆さんに、役立つ内容をお届けします。
コーチングスキルを活用したマネジメント

コーチングスキルを活用したマネジメントでは、部下やチームメンバーが「自ら考え、行動する力」を信じ、その成長に伴走する姿勢が求められます。対話を通じて相手が持っている可能性を引き出し、対話や問いかけによって思考や行動を促し、深い信頼関係を築きます。
管理職は「教える人」から「信じる人」へと役割を変え、部下自身が強みや課題を認識し、成長へと自発的に動き出すきっかけをつくります。それが現代の管理職に求められるリーダーシップのかたちです。
なぜコーチング型マネジメントが注目されているのか?
ビジネス環境の変化とマネジメントの限界
現代のビジネス環境は、変動性・不確実性・複雑性・曖昧性を特徴とする「VUCA」の時代に突入しています。このような環境では、あらかじめ用意された正解が通用しにくく、メンバー一人ひとりが変化に適応し、自ら考えて動く力を求められています。
しかし、従来のように「上司が答えを示す」「言って聞かせる」マネジメントスタイルでは、こうした人材を育てることは困難です。上司による一方通行の指示では、部下の内発的な動機や主体性が引き出されにくく、対応力のあるチームづくりにつながらないのです。
管理職の現場で起きていること


管理職の多くが「部下の育成」や「チーム運営」に悩み、プレイヤー業務とマネジメント業務の両立に苦慮しています。実際に、プレイヤー業務に50%以上の時間を割くマネージャーが多く、部下の育成や対話に十分な時間を取れない状況が続いています。
- プレイングマネージャーとして、日々の業務に忙殺されている
- Z世代をはじめ、価値観やキャリア観の異なるメンバーが増えている
- 「育成したい」という思いはあっても、関わる時間も余裕もない
結果、管理職自身が「自分がやった方が早い」と判断して手を動かしてしまい、部下の自律性や成長機会を奪ってしまうという悪循環に陥るケースも少なくありません。
コーチング型マネジメントというアプローチ
こうした現場の複雑な課題に対し、いま注目されているのが「コーチング型マネジメント」です。コーチング型マネジメントとは、“部下を動かす”のではなく、“部下が自ら動く”状態をつくるための関わり方です。特徴的なのは、答えを与えるのではなく、「問い」を通じて相手の思考を促すという点にあります。
- 「この仕事、どう進めてみようか?」
- 「最近、どんなことに迷いを感じている?」
といった問いかけが、部下自身の気づきや意志決定のきっかけになります。小さな対話の積み重ねが、やがて“自走するチーム”の土台を築いていくのです。コーチング型マネジメントは、長時間の1on1が必要というわけではありません。むしろ、忙しい管理職だからこそ、「問い方」や「聴き方」を磨き、限られた時間で最大限の関わりを実現するスキルとして活用できます。
つまり、関わる“量”を増やせない状況でも、“質”を高めることで部下の成長支援は十分に可能なのです。
ビジネスコーチングについてくわしく知りたい方はこちらの記事もご覧ください。
【コーチ監修】ビジネスコーチングとは?|ティーチングとの違いやメリット・導入ステップなど徹底解説
コーチングの基本手法

ここでは、管理職が日々のマネジメントに取り入れやすい、実践的なコーチングスキルをご紹介します。
① 傾聴(聴く力)
傾聴とは、相手の話の「内容」だけでなく、その奥にある感情や価値観まで受けとめようとする姿勢です。表面的に話を「聞く」ことと、本当に「聴く」ことはまったく違います。相手が言葉にしていない想いや葛藤に注意を向けることで、信頼関係が深まり、相手自身も安心して本音に触れられるようになります。
コーチング型マネジメントにおいては、上司が「ちゃんと聴いてくれている」「自分を理解しようとしてくれている」という感覚が、部下の自己開示を促し、結果的に自己理解や主体的な行動を引き出す土台になります。
傾聴には、うなずきや相づち、沈黙を待つ、問い返すといった具体的なスキルがありますが、最も大切なのは「相手を理解しようとする姿勢」です。多くのマネージャーは、問題を早く解決しようと話を聴きながら解決案を出してしまう傾向がありますが、傾聴の目的は「問題解決」ではなく、「相手の思考を促すこと」です。相手が自分の言葉で考え、気づき、整理するプロセスを支える。それが、傾聴の持つ力です。
POINT
- 「正しく聴く」より、「丁寧に関わる」ことを大切に
- アドバイスを急がず、相手の思考を信じて待つ
- 自分の解釈ではなく、相手が見ている世界を想像する
②質問(問う力)
コーチングにおける「質問」とは、相手の思考を深めるための“きっかけ”です。人は問いを投げかけられると、無意識に内面を探り、自分の言葉で整理しようとします。そのプロセスが、気づきや納得、そして行動の原動力につながるのです。だからこそ、コーチング型マネジメントでは、「教える」よりも「問う」ことが重要になります。
特に効果的なのは、“YES/NO”で終わらないオープンクエスチョンです。正解を与えるのではなく、考える余白のある問いかけを通じて、相手の主体的な意思決定を支えていく。これが、管理職に求められる「問う力」です。
オープンクエスチョンの例
- 「どうしてそう思ったの?」
- 「理想の形ってどんな状態?」
- 「何か他に選択肢はありますか?」
- 「もし制約がなかったとしたらどうしますか?」
問いかけの意図が伝わらないと、相手は本音を話しにくくなります。詰問や誘導にならないよう、ペースや雰囲気に配慮し、安心して答えられる空気感をつくることも大切です。
③ フィードバック(気づかせる力)
フィードバックは、相手に新たな視点を届け、気づきを引き出すためのコミュニケーションです。ときには相手が自覚していない行動のクセや、思考のパターンに気づいてもらうことで、成長へのきっかけをつくることができます。
その際に大切なのは、相手を評価・判断するのではなく、事実や、自分の視点・チームとしての観点をもとにしたフィードバックを伝えること。あくまで対等な立場で、最後の判断を相手に委ねることがコーチングの基本姿勢です。
フィードバックの例
- 「今日はずっと◯◯さんの話をしていますね。あなた自身はどうしたいのでしょうか?」
- 「あなたはそう感じるのですね。私たちからはこう見えていますよ」
相手の思考に“別の視点”を加えることで、思考の構造が整理され、行動の可能性が開かれていく。それがフィードバックの本質です。
導入企業の声に見る「変化」
実際にビジネスコーチングを導入した企業では、以下のような変化が報告されています。
上司が“聞ける人”になることで、1on1の質が変わった
静岡放送株式会社では、1on1を導入したものの「上司が自分の話ばかりしてしまう」といった課題を抱えていました。コーチングを受けたミドルマネージャーたちは、「自分がいかに“聴けていなかったか”に気づいた」と振り返っています。
- 「1on1の本当の意味合いを理解できたことで、部下ときちんと向き合えるようになった」
- 「傾聴される体験を通じて、対話のあり方が変わった」
その結果、メンバーとの関係性が改善し、組織全体の対話の質が底上げされました。組織のエンゲージメントや成果にも好影響。
(出典:mento導入事例 静岡放送株式会社)
管理職の“聴く力”が現場を変えた
パナソニック インダストリー株式会社では、従来のマネジメント研修に加え、コーチングを取り入れたことで、参加者の“聴く姿勢”が大きく変化しました。
研修主催者からは「1年前と比べて、参加者の反応やスコアが劇的に良くなった」「何か施策を変えたのか?」という声が上がったほどで、組織の“ソフト面”を強化したことが、研修という“ハード面”の成果にもつながったと実感されています。
(出典:mento導入事例 パナソニック インダストリー株式会社)
その他のビジネスコーチングの事例についてはこちらの記事をご覧ください。
マネジメント課題を解決するビジネスコーチング事例8選
まとめ|管理職にこそ必要な「問いかける力」
マネージャーは、指示する人ではなく、部下の可能性を引き出す人へと変わりつつあります。近年では、多くの企業が「コーチング型マネジメント」への移行を進めており、傾聴・質問・承認といったスキルを土台にした対話が、成果につながる時代になっています。
「部下が育たない」「思うように動いてくれない」と感じたとき、それは“育て方”を見直すタイミングかもしれません。 ビジネスコーチングの基本を押さえることで、マネジメントはもっと自然で、対話的で、成果につながるものになります。
まずは明日の1on1で、「あなたはどう思う?」と、ひとつ“問い”を投げかけてみてください。その小さな一言が、部下の内省を促し、チームの未来を変えるきっかけになるかもしれません。