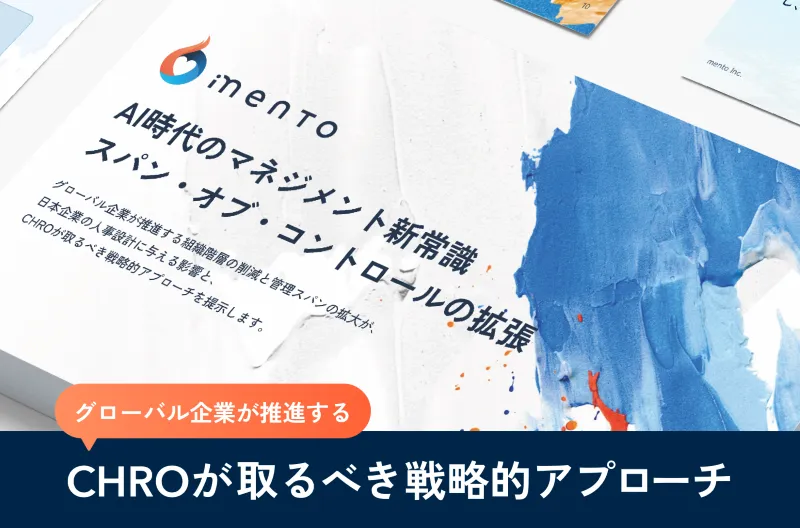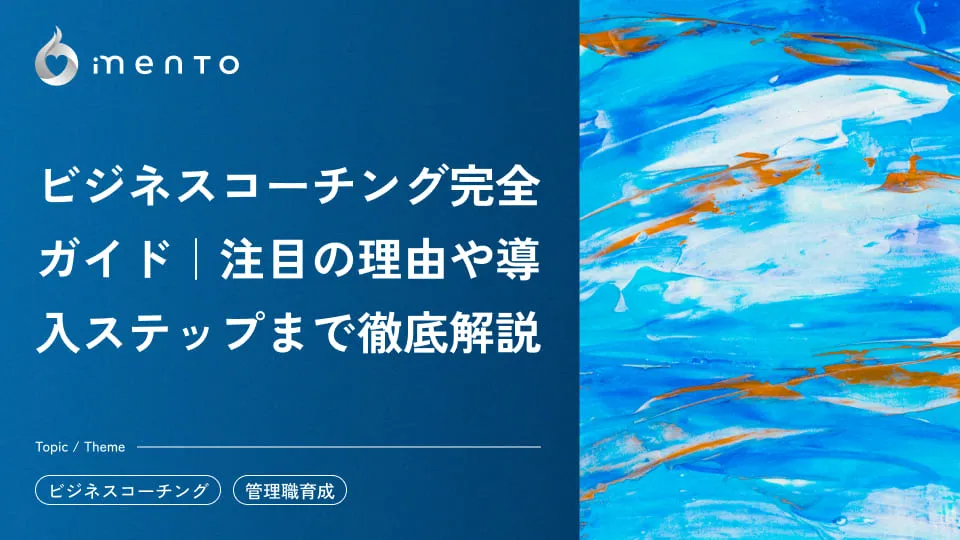


【コーチ監修】ビジネスコーチング完全ガイド|注目理由、導入ステップなど人事部担当者向けに徹底解説
著者:株式会社mento コーチサクセス/HR 鈴木 麻理子
2021年よりmento登録コーチとして活動を開始。2022年にmentoへ入社し、コーチサクセスとして約200名の登録コーチのサクセス・サポートを担いつつ、企業のミドルマネジメント層をメインにコーチングを提供。有償セッション経験時間は850時間超。(一財)生涯学習開発財団認定プロフェッショナルコーチ資格保有
INDEX
変化が激しく、先を見通しにくい時代。企業の持続的な成長には、一人ひとりの力を引き出し、組織全体のパフォーマンスを高める仕組みが欠かせません。
こうした中で、急速に注目を集めているのが「ビジネスコーチング」です。近年では、管理職育成や組織開発を目的に導入する企業が増え、エンゲージメント向上や離職防止などの成果にもつながっています。
本記事では、ビジネスコーチングの定義、導入ステップ、企業の声、費用対効果(ROI)の考え方までを網羅。さらに、サービス選定で失敗しないためのポイントを、現役コーチの知見を交えて解説します。
導入を検討している皆さまに向けて、実務に活かせる視点をお届けします。
ビジネスコーチングとは
ビジネスコーチングを正しく理解し、効果的に導入するためには、まずその定義や他の人材育成手法との違いを把握しておくことが重要です。

コーチングの定義と、ビジネス領域における活用意義
コーチングとは、対話を通じて相手(クライアント)の内省を促し、自ら気づき、行動を選択・実行できるよう支援する手法です。「話す → 気づく → 変わる → 続ける」というプロセスにより、クライアント自身の変容を促進します。
これをビジネス領域に応用したものが「ビジネスコーチング」です。対象は主に経営層、管理職、次世代リーダーなどのビジネスパーソンで、企業の戦略や役割に沿いながら、対話の中でクライアント自身の価値観や感情にも丁寧に向き合い、内発的な動機づけや、個々の強みを活かしたリーダーシップの発揮を支援していきます。

メンタリング・ティーチングとの違い
人材育成の手法には、コーチングと類似するものとしてよく「メンタリング」や「ティーチング」が挙げられます。これらは一見似ているようで、目的や関係性、アプローチ手法に大きな違いがあります。
育成対象のレベルや目的によって最適なアプローチは異なりますが、主体性の高いマネジメント層や、自らの意思で変容する力を求められる人材にとって、コーチングはとくに有効です。従来の指導・育成方法だけでは補いきれない、より“自走できる人材”の育成が、コーチングの強みといえるでしょう。
世界的に注目されている背景
ビジネスコーチングは今、世界のリーディング企業を中心に、経営戦略や人材開発の柱として導入が進んでいます。
フォーチュン500企業の7割が導入
米国の主要企業に関する調査*では、フォーチュン500企業の約77%がコーチングに高い効果があると評価。経営層がコーチを活用し、パフォーマンスや意思決定を支援するのは、もはやスタンダードになりつつあります。
*出典:「Executive Briefing: Case Study on the Return on Investment of Executive Coaching」(2001年)
こうした潮流は、人を動かすためには“管理”よりも“信頼関係”が鍵となるという考え方の広まりとも一致します。
ビジネスコーチングはまさに、この「信頼関係を築きながら、個人の内発的な動機を引き出し、自律的な成長を促すアプローチ」として、その価値があらためて世界的に見直されています。
なぜ今、日本でもビジネスコーチングが注目されるのか

いまや企業規模や業種を問わず、ビジネスコーチングの導入が進んでいます。本章では、主に「育成」「定着・組織力強化」の観点から、その背景をひもときます。
管理職の育成に“個別最適”で対応できる
従来の管理職研修は、階層別に同じ内容を提供する「一律型」が主流でした。しかし実際には、マネージャーごとに置かれた状況や課題は異なり、画一的な研修では十分な成長支援が難しいのが現状です。
そこで注目されているのが、一人ひとりの課題や特性に応じた“個別最適”な支援ができるビジネスコーチングです。型にはまった指導ではなく、対話を通じて自身の課題に気づき、思考を深め、行動を変えるプロセスを支援します。
これにより、表面的なスキル習得にとどまらず、内面的な変化やリーダーシップの深化といった、より本質的な成長を促すことが可能になります。
VUCA時代における、変化に強い組織づくり
市場環境や働き方、テクノロジーの変化が加速するいま、企業には「変化にしなやかに適応できる組織づくり」が求められています。
ビジネスコーチングは、そうした組織の土台となる“自律性”や“共通目的の理解”、“部門間の信頼関係”を現場レベルで醸成するアプローチです。画一的な号令や研修では届きにくい、現場の意識・行動の変化を引き出すことができます。
また、コーチングによって生まれる対話の文化は、従業員のエンゲージメント向上や離職防止といった観点でも注目されています。変化の激しい環境下で、主体的に動ける組織風土を育てる可能性のあるアプローチの一つとして、関心が高まっています。
上司に求められるコミュニケーションスキルの変化
価値観や働き方の多様化が進む中で、上司に求められるコミュニケーションスタイルも大きく変化しています。
今の現場で必要とされているのは、部下の考えを引き出し、内発的な動機づけを促す“対話型”のマネジメントです。傾聴・承認・問いかけといったコーチングスキルは、単なるコミュニケーションテクニックではなく、組織のエンゲージメントや生産性に直結するマネジメント基盤として機能します。
ビジネスコーチングは、管理職自身が傾聴や問いかけを受ける体験を通じて、自分の思考や感情に気づき、メタ認知を高める契機となります。その実感を通じて、対話的な姿勢をマネジメントに活かすようになるケースも多く、導入する企業が増えています。
ビジネスコーチングを導入するメリット

導入によって得られるメリットは、受講者本人の変化にとどまりません。企業や人事部門の視点から見ると、組織全体の課題解決や競争力強化に繋がる、複数の重要なメリットがあります。
管理職・リーダー層の意思決定力とマネジメント力の底上げ
コーチングによって、思考の整理、自己認識の深化、フィードバックの受容力が高まり、リーダーがより効果的な判断を下せるようになります。結果として、現場での意思決定の質が上がり、マネジメントの一貫性やスピードが向上します。これらは、戦略の浸透や実行力の向上に直結します。
人事施策の本質的な実行力を高める
制度設計や研修、1on1などの施策は、現場で“自分ごと”として理解・実践されて初めて成果を生みます。
ビジネスコーチングは、対話を通じてその橋渡しを担い、施策の理解促進や行動定着をサポート。結果として、施策全体の実効性や浸透度が高まります。
人事施策×ビジネスコーチングについてもっと知りたい方はこちらの記事もご覧ください。
管理職育成を次のステージへ──ビジネスコーチングで突破する現場課題
人的資本経営の流れに対応した、施策評価の視点
人的資本への投資やその可視化が求められる中で、どのような育成施策においても「効果をどう捉えるか」が重要な論点となっています。
ビジネスコーチングも例外ではなく、導入にあたってはエンゲージメントの変化や行動変容などを定性的・定量的に捉える工夫が求められています。こうした視点は、経営層への報告や施策全体の継続的な見直しにも活用され始めています。
ビジネスコーチングの選び方

コーチング導入の成否は、サービスの選定段階で大きく左右されます。支援対象の階層や進め方、コーチの質などはサービスごとに異なり、「想定した効果が出なかった」「現場で定着しなかった」といった失敗にもつながりかねません。
1.コーチの質は担保されているか?
ビジネスコーチングの成否を分ける最大の要素は、やはり「誰がコーチングを行うのか」です。経歴や資格の有無に加え、以下のような観点でコーチの育成・評価体制も確認することが大切です。
✓ 自社と類似業界や階層への支援実績があるか
✓ 特定のコーチに依存せず、一定の品質基準を満たす体制があるか
✓ 継続的なトレーニングやフィードバック体制が整っているか
信頼性の高いサービスは、こうした観点での情報を開示しており、実績ベースで比較検討することが可能です。
2.導入後のサポート体制は充実しているか?
いわゆる「カスタマーサクセス(CS)」と呼ばれる導入後のサポート体制も、成果を出す上で重要な要素です。単発のセッション提供にとどまらず、以下のような継続支援があるかどうかを確認しましょう。
✓ 人事・管理職への定期的なフィードバックやフォローがあるか
✓ 社内への浸透を支援するレポート提出や報告会の開催があるか
✓ トラブル対応やコーチ変更に柔軟に対応できる体制があるか
こうしたCSの手厚さが、現場での“つまずき”を減らし、社内定着を加速させます。
3.効果測定の仕組み(ROI)は可視化されるか?
ビジネスコーチングは、定性的な印象で評価されがちですが、経営視点での意思決定には「成果の可視化」が欠かせません。以下のような仕組みが整っているかをチェックしましょう。
✓ エンゲージメントスコアや行動変容の定点観測が可能か
✓ 個人だけでなく、組織単位での成果レポートが得られるか
✓ ROI(投資対効果)を可視化するフレームや試算支援があるか
これらの仕組みは、経営層への報告や、将来的な投資判断の根拠としても活用できます。
自社にとって最適なビジネスコーチングを選び、成果につなげていくには、「価格」「知名度」だけにとらわれず、今回紹介した3つの視点を軸に、複数の候補を丁寧に比較検討していくことが重要です。
導入ステップと社内浸透のコツ

ビジネスコーチングは、導入しただけでは効果が得られません。成果につなげるには、導入から社内への浸透までを段階的に設計し、丁寧に実行することが求められます。
導入は“一斉展開”よりも“段階的展開”が鍵
まずは、ニーズの高い管理職層や、変化の起点となる中核人材を対象に絞ってスタートするのが効果的です。小規模な成功事例を積み上げることで、社内に実績と信頼を築き、スムーズな展開につなげることができます。
組織の特性に合わせた着実な展開方法
組織文化や課題、マネジメント層の成熟度によって、最適な進め方は異なります。たとえば、すでに1on1やフィードバック文化が浸透している企業であれば、コーチング導入のハードルは比較的低くなります。一方、対話の習慣が根づいていない現場では、まずは“話す場をつくる”といった土台づくりから始める必要があります。
「社内に何を定着させたいのか」という目的を明確にしつつ、現場との温度差に配慮したステップ設計が求められます。
社内浸透のコツ
導入の鍵を握るのは、対象者の納得感です。制度としてただ案内するのではなく、「この取り組みが自分や組織にとってどんな意味を持つのか」を実感してもらう対話の機会が重要です。
また、初期導入の成果を社内に共有する仕組みを整えることで、他部門や他階層への波及を促しやすくなります。上司や人事担当者が受講者の変化を言語化し、周囲に伝えることも浸透を後押しします。
次章では、実際にビジネスコーチングを導入した企業の声をご紹介します。導入の背景や成果を知ることで、自社での活用イメージをさらに具体化できるはずです。
導入ステップと社内浸透のコツについてもっと知りたい方はこちらの記事もご覧ください。
【5ステップ】ビジネスコーチング導入と浸透の実践ガイド
ビジネスコーチング利用企業・利用者の声
ここからは、実際の現場でどのような変化をもたらしているのかをお届けいたします。
パナソニック インダストリー株式会社
画一的な研修では変化が起きない。“個別最適”の必要性から導入へ
変化を可視化しやすい「社内公募制」で、取り組みの浸透と意欲の高さが明確になりました。
変化の声:
- 募集開始からわずか1日で100人が応募、1年間で途中離脱者はゼロ
- 部下との会話が増え、コミュニケーションの質が向上
株式会社デンソー
不安の多い異動・海外赴任に対応するため、自己変容を支援する仕組みを構築
個人の変容を起点に、組織全体にポジティブな連鎖が生まれています。
変化の声:
- これまでの枠を超えた行動が生まれ、マネジメントスタイルに変化が現れた
- コーチングによって内面の気づきが深まり、その変化が周囲にも波及
株式会社静岡新聞社・静岡放送株式会社
組織改革の実現に向けて、マネジメント層のリーダーシップを強化
対話と内省を通じて、変化に向き合うリーダーを着実に育成しています。
変化の声:
- 自分なりの判断軸を持ち、影響力を広げるリーダーへと成長
- 安心して本音を話せる対話の場が、成長の土台となった
電通グループ(dentsu Japan)
迅速な意思決定と共通認識の醸成を図る、経営変革の一手として
複雑な組織において、共通言語を育てる手段として機能しています。
変化の声:
- 戦略を明確に言語化できるようになり、スムーズな意思決定が可能に
- 対話の質が高まり、チームの協力体制がより強固に
ビジネスコーチングの事例についてもっと知りたい方はこちらの記事もご覧ください。
マネジメント課題を解決するビジネスコーチング事例8選
投資対効果の考え方
【このセクションのポイント】
✓ 定量化が難しい効果を「可視化」する工夫が重要
✓ 評価指標はES、360度評価、離職率の変化など
✓ ROIはコスト削減・生産性向上・制度定着率から算出
✓ 成果を最大化するには、目標定義・継続支援・報告体制がカギ
ビジネスコーチングの価値は、「人の変化」を通じて生まれる成果にあります。しかしその多くは、行動や関係性の変化といった定性的なものであり、導入効果の可視化に難しさを感じる企業も少なくありません。
定量化の難しさと、一般的な評価指標
コーチングによる変化は、「離職率の改善」や「マネジメントの質の向上」など、すぐに数字に表れにくいものです。それでも、エンゲージメントスコアや360度評価、定着率などの指標を活用することで、変化を可視化する手がかりを得ることができます。
- エンゲージメントスコア(ESスコア):
組織全体の意欲や満足度を測る定点観測指標 - 管理職の評価スコア:
360度評価などを活用して、マネジメント力や信頼関係の変化を可視化 - 離職率:
コーチング導入前後の変化を比較し、定着度を確認
投資対効果(ROI)の考え方

ROI(Return on Investment)は、「投資額に対してどれだけのリターンが得られたか」を示す定量的な指標です。ビジネスコーチングにおけるROIは、以下のような効果を組み合わせて捉えることができます。
- 離職防止によるコスト削減:
たとえば、年間の離職率が数%改善することで、採用・教育にかかるコストを数百万円単位で削減できる場合もあります。 - 生産性向上による利益貢献:
マネージャーの業務効率や意思決定スピードが上がることで、プロジェクトのリードタイム短縮やチームのアウトプット向上につながるケースも多く見られます。
※なお、ROIの直接的な構成要素ではないものの、コーチングを通じて1on1やキャリア支援制度の理解・定着が進むことで、既存施策の活用度や効果が高まりやすくなる点も、導入企業から注目されています。
効果を最大化するためのポイント

ROIは効果を可視化する手段の一つですが、数字を示すだけでは十分ではありません。成果を最大化するには、導入設計や社内展開の工夫が欠かせません。ここでは、ROIをより実効性あるものにするための3つの工夫を紹介します。
- 事前に「何を成果とするか」を定義する:
目的やゴールが曖昧なままでは、成果も測定できません。「離職率の低下」「評価面談の質の向上」「エンゲージメントスコアの向上」など、明確な目標設定がカギになります。 - 定性・定量の両面で変化を捉える:
数値だけでなく、「チームの雰囲気が変わった」「部下が自分から話すようになった」といった定性的変化も、社内で共有・蓄積することで説得力を増します。 - 継続的なフォローと報告の仕組みを整える:
導入時だけでなく、実施中や終了後にも経過観測を行い、経営層に定期的に成果を共有することで、継続投資の意思決定を後押しできます。
「成果が見えづらい」と言われることもあるビジネスコーチングですが、適切な指標設計と運用次第で、投資対効果は明確に示すことができます。
よくある疑問(FAQ)
ビジネスコーチングの導入を検討する中で、「本当に自社に必要なのか?」「どれほど効果があるのか?」といった疑問や不安を抱く方も少なくありません。
ここでは、企業人事からよく寄せられる質問をピックアップし、導入判断の参考となる考え方をご紹介します。
- Q1. どんな人がコーチングを受けるべき?
A:特にマネジメント層や変革のキーパーソンに有効です。
管理職やプロジェクトリーダーなど、組織の変化を担う立場にある人ほど、自らの意思決定や対人関係の質が業績に直結します。こうした層への1on1コーチングは、個別最適な支援として効果的です。 - Q2. 他の研修と何が違う?
A:知識のインプットではなく、“自らの気づき”を引き出す点が最大の違いです。
一般的な研修が「何を知るか」に重きを置くのに対し、コーチングは「どう考え、どう行動を変えるか」に焦点を当てます。課題が明確でない段階でも、内省を深め、行動変容を促すアプローチが可能です。 - Q3. 導入に失敗するケースとは?
A:目的が曖昧なまま導入し、現場で“他人事”になってしまうケースです。
「とりあえず取り入れる」では成果が出にくく、対象者の納得感や、社内の巻き込み設計が不十分な場合には定着も難しくなります。導入前に、支援の対象とゴールを明確にし、初期成果を社内で共有するステップ設計がカギとなります。 - Q4. 費用はどのくらいかかる?
A:対象者の数や支援の期間によって異なりますが、月数万円〜数十万円/人が一般的です。
料金は、セッションの回数・期間・対象層・コーチの質などによって大きく変動します。費用だけでなく、「効果測定の仕組みがあるか」「サポート体制が整っているか」といった要素もあわせて検討することをおすすめします。 - Q5.どのくらいの期間が必要?
A:6~12か月を1クールとするケースが多く、継続的に取り組むことで効果が定着します。
コーチングは単発で成果が出るものではなく、継続的な対話を通じて行動や考え方を変えていくプロセスです。まずは短期のトライアルからスタートし、現場の反応を見ながら拡張していく企業も多く見られます。 - Q6.オンラインでも効果はある?
A:オンラインでも、十分に効果を発揮します。むしろ時間・場所にとらわれず、継続しやすいというメリットも。
近年では、ビジネスコーチングの多くがオンラインで提供されています。対面と比べても、信頼関係の構築や深い対話に支障はなく、むしろ移動の負担がない分、定期的な実施や継続につながりやすいという声も増えています。セキュリティや接続環境の整備は必要ですが、全国・グローバル展開を視野に入れる企業にとっても、有効な選択肢です。
まとめ
ビジネスコーチングは、管理職育成や組織開発のあり方が問われる今、企業にとって“新しい当たり前”となりつつあります。従来の一方向的な教育では支えきれなかった現場の課題に対し、個別最適な対話を通じて行動変容を促す手法として、多くの企業で成果をあげています。
私たちmentoは、60,000時間を超えるコーチングを通じて、管理職が抱える「正解のない葛藤」と向き合ってきました。見えてきたのは、知識ではなく“気づき”が行動を変え、現場を動かすという事実です。スキルを教えるだけでは届かない領域にこそ、本質的な変化の鍵があると、私たちは考えています。
HR領域のあらゆる課題が見える化される一方で、実際に現場を動かす力が追いついていない──。だからこそ今、私たちはコーチングを通じて、一人ひとりの行動変容を支える仕組みづくりに本気で取り組んでいます。
ビジネスコーチングを、自社にとって本当に価値ある選択肢として活かしていく。その第一歩がここから始まることを願っています。