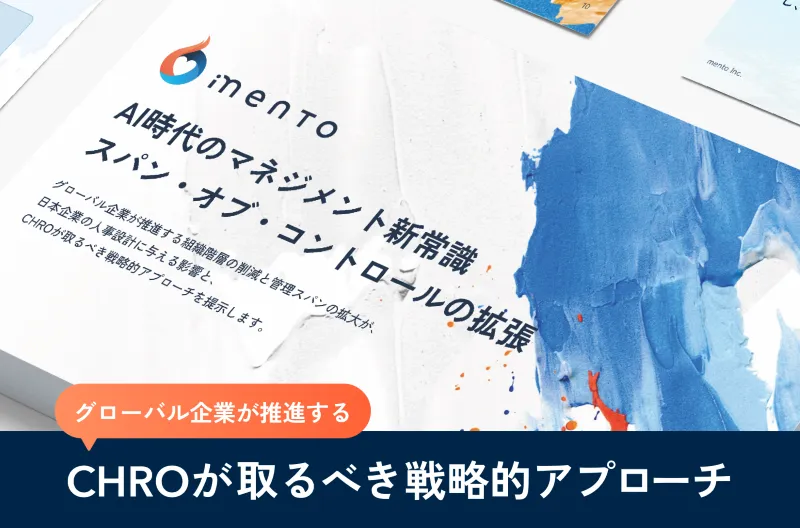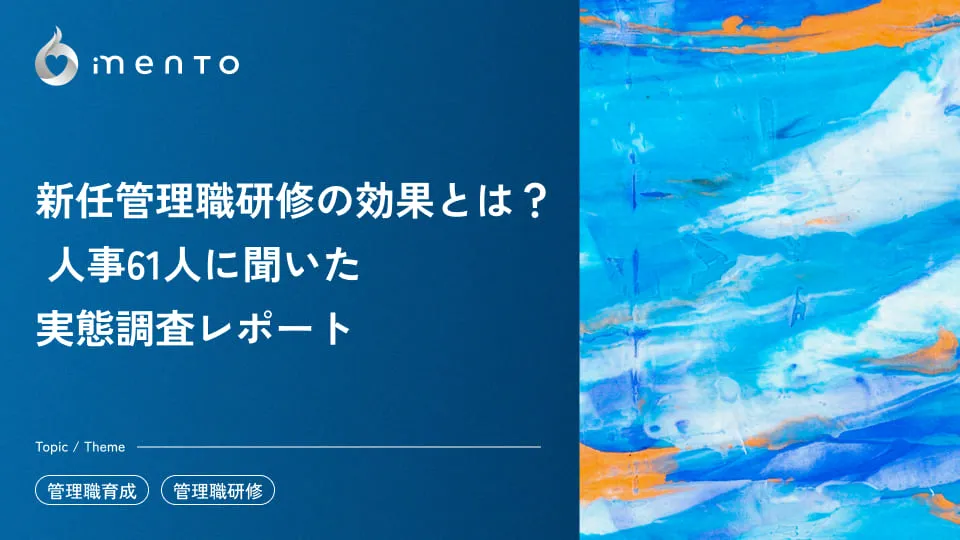


新任管理職研修の効果とは? 人事61人に聞いた実態調査レポート
著者:mento編集部
法人向けビジネスコーチングの提供を通じて、企業の人事課題解決を支援する専門チーム。「この国の総労働熱量をあげる」を理念に掲げ、実践知に基づいた情報発信を行っています。人材育成と組織力強化に関する豊富な知見をもとに、経営・人事領域に役立つコラムをお届けします。
INDEX
新任管理職は、プレイヤーからマネージャーへと役割が大きく変化し、業務面でもメンタル面でも多くの課題に直面します。企業の人事担当者は、こうした新任管理職をどのように支援し、早期に戦力化できるのかが大きなテーマです。
本記事では、mentoによる人事担当者61人への調査データをもとに、新任管理職研修の現状やよくある課題、近年注目されている「コーチング活用」の最新動向、現場での変化事例までを詳しく解説します。
研修が足りていない気がする、現場に定着しないと感じている方に向けて、他社の取り組みを知り、これからの施策設計に役立てるヒントが詰まった内容です。
なぜ今「新任管理職研修」の見直しが求められているのか?
新任管理職研修は、多くの企業で導入されていますが、「現場が変わった」という実感を持てている人事担当者は、どれだけいるでしょうか。
制度としての研修は整っていても、
● 昇格直後の混乱に十分に寄り添えていない
● スキルを学んでも、自信にはつながらない
● 現場の行動変容が起きず、効果が見えにくい
といった悩みを抱える企業は少なくありません。
プレイヤーからマネージャーへと役割が大きく変わるこのタイミングこそ、本来であれば最大の成長機会です。けれど、そこにまで手が届いていないという実感があるなら、今こそ支援のあり方を見直すタイミングかもしれません。
調査概要とサマリー|現場の“違和感”を可視化した61人の声
今回の調査は、mentoが人事担当者を対象に実施したアンケート結果をもとに、新任管理職研修の現状と課題、そしてコーチングへの期待を明らかにしたものです。
調査概要
- 調査名:新任管理職研修に関する実態調査
- 調査期間:2024年4月22日〜4月30日
- 対象者:mentoセミナーや商談等で接点のあった人事担当者(担当者〜役員クラス)
- 有効回答数:61名
- 調査方法:メールによるアンケート回答
サマリー(主な調査結果)
本調査では、企業の人事担当者61名に対して、新任管理職研修の実施状況や効果、コーチングへの期待についてアンケートを実施しました。その結果、各社が育成に注力している一方で、制度と現場の間にあるギャップが明らかになりました。

1.人事が最も注力しているのは「次世代リーダー育成」
人事担当者の30%が「次世代経営層・リーダー層の育成」を最重要ミッションと回答。単なるスキル習得ではなく、組織の未来を担う人材の、質的な転換が求められている現状が見えてきます。変化が求められています。

2.新任管理職研修は、全員に実施している企業が約半数
「新任管理職全員に研修を実施している」と回答したのは48.3%。「一部の新任管理職のみに実施」は25.0%、「未実施だが今後実施したい」も23.3%と多く、支援のスタートラインが分岐している状況です。

3.研修を“業務に活かせている”と感じるのはわずか3割
研修を受けた新任管理職のうち、実際に業務に活かせていると感じているのは32.6%でした。研修内容の設計や、現場での実践との接続に課題が残っていることがうかがえます。

4.コーチングへの期待は「育成力」と「キャリア支援」
コーチング受講に対しては「メンバー育成力の向上」(83.3%)、「メンバーのキャリア支援」(56.7%)への期待が高く、一方的に“教える”のではなく、相手の考えや意欲を“引き出す”ような支援スタイルへのニーズが強まっています。
これらの調査結果は、「制度と現場」「知識と実践」「導入と定着」というギャップを浮き彫りにしており、同時に、“新しい支援の形”への模索がすでに始まっていることも示唆しています。
新任管理職研修の実態と課題
研修実施の現状
新任管理職研修は多くの企業で導入されていますが、「全員を対象に実施している」と回答したのは約半数(48.3%)にとどまります。残りは選抜型や一部実施にとどまり、そこにはリソースや運用体制の制約が影響していると見られます。
特に中小企業では、研修を実施する余力が確保しづらく、組織規模による育成格差も顕著になっています。こうした“スタートラインの差”は、昇進後の支援機会や育成の手厚さに大きく影響する要因となっています。
研修効果の定着課題
研修を受講しても、現場での実践や行動変容につながっていると感じている人は約3割にとどまります。単なる知識の習得にとどまり、日々のマネジメント行動に落とし込めていない現状が浮かび上がります。
その背景には、以下のような構造的課題が見られます。
- 研修内容が現場の課題や個別の悩みに十分フィットしていない
- 研修後のフォローや伴走支援が弱く、学びが風化してしまう
- 管理職本人が「自分ごと化」できず、学びを行動に移すきっかけがつかめない
学習機会は提供していても、「現場で使える・使いたくなる」状態をつくれていなければ、変化は起きません。
人事担当者の課題感
人事担当者の多くは、「次世代リーダー育成」「管理職育成」を最優先ミッションとしています。一方で、現場のマネージャーたちが直面しているのは、個別具体的で繊細な課題です。
- メンバーを育てられない
- キャリアの支援がうまくできない
- 年上部下との関係に悩んでいる
- 業務改善の優先度が見極められない
といった現場の課題にどう向き合うかは、画一的な研修では対応が難しい領域です。また、研修の効果測定やKPIの設計、行動定着の仕組み化といった運用面も課題となっており、「やっているのに、効いている実感がない」という悩みを抱える人事担当者も少なくありません。
このように、制度としての整備は進んでいるものの、現場での実践や支援設計には多くの余白が残されています。次のセクションでは、そうした“届かない支援”を補完するアプローチとして注目されている「コーチング」について掘り下げていきます。
新任管理職向けのコーチングとは

集合研修では届かない、個別の葛藤にどう向き合うか
- 「自分でやった方が早い」
- 「部下に仕事を任せられない」
- 「1on1の正解が分からない」
- 「メンバーが主体的に動いてくれない」
新任管理職が抱える悩みの多くは、技術的な正解があるわけではなく、むしろ“マネジメントの葛藤”に近いものです。プレイヤー時代とは異なる視座・責任を求められ、誰かに答えを教えてもらうのではなく、「自分で考え、決め、伝える」ことが求められる局面で立ち止まってしまいます。
従来型の集合研修や座学では、こうした個別の課題に十分対応することは難しく、そこで取り入れられているのが「コーチング」という手法です。
コーチングの役割と効果
コーチングは、問いかけや対話を通じて、本人の中にある考え・感情・価値観を言語化し、納得感あるアクションへとつなげていくプロセスです。
特に新任管理職においては、以下のような効果が期待できます。
- 自分らしいリーダー像や目標を明確化できる
- 現場の葛藤を言語化し、実行可能な行動に落とし込める
- 部下との対話力やフィードバックの質が向上する
- エンゲージメントや組織風土への好影響が波及する
単に「やり方を学ぶ」だけでなく、「どう在りたいか」「なぜそれが大事か」を明確にすることで、行動へのブレない軸が育まれます。
実際によくあるコーチングテーマ
新任管理職がコーチングで相談するテーマは多岐にわたります。
- 管理職としての責任に自信が持てない
- 部下に仕事を任せられない
- メンバーが主体的に動かない
- 1on1コミュニケーションの難しさ
- 厳しいフィードバックができない
- 年上部下との関係構築に悩んでいる
- 自分らしいリーダーシップを模索している
- 孤独感を感じている
- 組織の理想像やキャリアビジョンを明確にしたい
これらの問いには、正解はありません。だからこそ対話によって本人の中から答えを見つけていくコーチングが有効なのです。
企業事例:
パナソニック インダストリー株式会社
パナソニック インダストリー株式会社では、部課長クラスの管理職100名に対して、1年間のコーチングプログラムを導入。「仕事を抱えすぎる」、「1on1に自信が持てない」、「昇進直後で不安」などの個別課題に対してコーチが伴走しました。
その結果、このような変化が現場で報告されました。
- 部下への仕事の任せ方に変化が生まれた
- 1on1の質が向上し、育成に時間をかけられるようになった
- 自分のリーダー像を言語化できるようになった
さらに導入後、エンゲージメント向上や組織風土への満足度向上といった数値的成果にもつながっています。
(出典:mento導入事例 パナソニック インダストリー株式会社)
コーチングがもたらす現場の変化
コーチングを取り入れた管理職たちは、対話を通じて部下の主体性や関係性の質を高め、組織にポジティブな変化をもたらします。
- 本音の対話が増える
- 心理的安全性が高まり、率直な言葉が交わされる
- 主体的な行動が促される
- 課題に対する“自分なりの意味づけ”が行動につながる
- マネジメントの負荷が分散される
- 状況把握や適切な介入がスムーズになり、支援が届きやすくなる
さらに、部下の課題そのものに対処するのではなく、「その課題に本人がどう向き合っているか」に焦点を当てることで、部下自身が自ら動き出すきっかけが生まれます。
まとめ
新任管理職研修は多くの企業で導入されていますが、現場での実践や行動変容には依然として課題が残ります。制度として研修を整備しても、「自分にはできない」「学んだけれど使えない」という声が消えない理由は、支援の設計が“届ける”ことにとどまり、“効かせる”仕組みまで届いていないからかもしれません。
一方、コーチングの導入は「メンバー育成力」や「キャリア支援」への期待を背景に、個別課題への対応や現場での変化を生み出す有効な手段として注目されています。今後求められるのは、知識伝達型の集合研修と、対話をベースにした個別コーチングの組み合わせ。そして、継続的なフォローと現場伴走を通じて、管理職一人ひとりの「あり方」に向き合う支援をつくることです。
「教える」から「支える」へと、管理職育成は今まさに変わろうとしています。そしてその変化の先に、組織全体の活性化と、未来を担うリーダーの成長があるはずです。