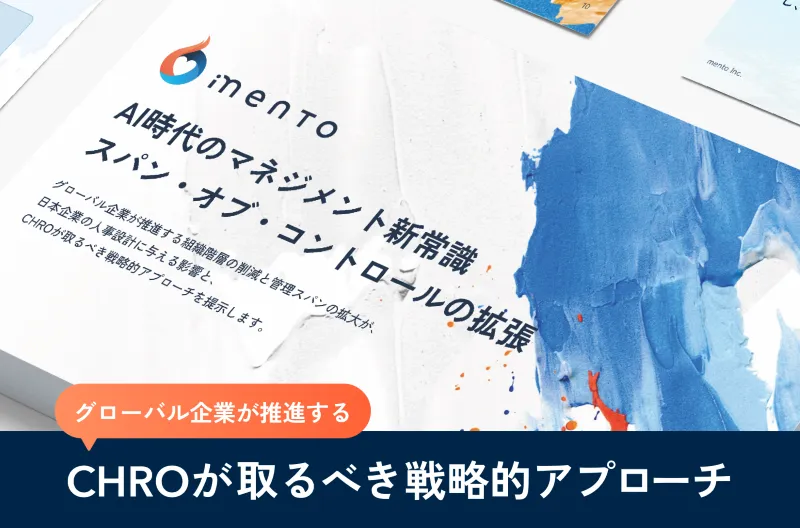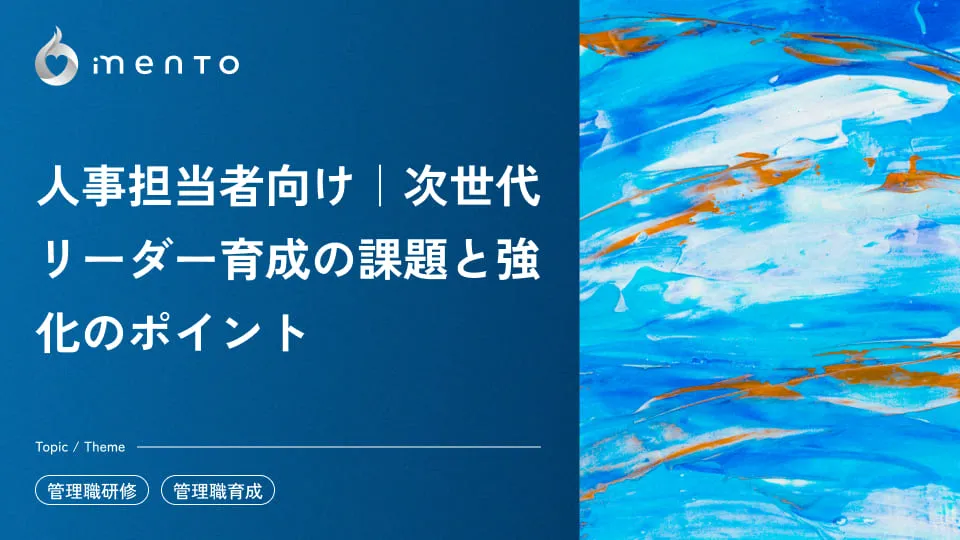


次世代リーダー育成の課題と強化のポイント
著者:mento編集部
法人向けビジネスコーチングの提供を通じて、企業の人事課題解決を支援する専門チーム。「この国の総労働熱量をあげる」を理念に掲げ、実践知に基づいた情報発信を行っています。人材育成と組織力強化に関する豊富な知見をもとに、経営・人事領域に役立つコラムをお届けします。
INDEX
「次世代を担うリーダーを育てたい」と思っても、実際にどこから手を付けるべきか迷っている。そんな悩みを抱える人事担当者は少なくありません。現場に任せきりになっていたり、育成施策が形骸化していたりと、リーダー育成に本腰を入れられていない企業も多いのが実情です。
本記事では、次世代リーダー育成の進捗を可視化する方法から、主要な課題の強化ポイント、さらに実際の企業事例までを紹介します。今後の育成施策の立案・見直しに役立つ実践的な内容をお届けします。
なぜ今、「次世代リーダー育成」が重要なのか
企業環境の変化とリーダー像の変化
企業を取り巻く環境は、かつてないスピードで変化しています。不確実性が高まる中、これまでのリーダー像では通用しない場面も増えています。そんな状況下で今求められているのは、変化にしなやかに対応し、周囲と信頼関係を築きながら組織を導ける「次世代リーダー」です。
従来型リーダーシップの限界
成果主義やトップダウン型の意思決定だけでは、組織は変化に対応しきれません。個人の価値観や多様な働き方が尊重されるこの時代には、共感力・対話力・自律的な意思決定ができる“新しいリーダー像”が求められています。
次世代リーダー育成のよくある課題
多くの企業が「次世代リーダー育成は重要」と認識しているにもかかわらず、いざ育成に取り組もうと動き出しても、全体の設計が曖昧だったり、現場にどう落とし込むか悩んだりしてしまうケースがあります。課題は分かっていても、具体的な打ち手が見つからないというような状態が、次世代リーダー育成の現場では頻繁に起きています。
- 全体像が描けていない
場当たり的な施策で、育成が点在している
- 成果が見えにくい
施策が形骸化し、振り返りや効果検証がされていない
- 「誰を育てるか」が曖昧
育成対象の基準が明確でなく、選定が属人的になりやすい
これらの課題を放置すれば、育成の精度も成果も上がらず、結果的に将来の経営層不足につながってしまいます。
次世代リーダー育成の進捗をチェックする
まずは、自社の取り組み状況を客観的に可視化しましょう。感覚や印象ではなく、体系的に現状を捉えることがスタート地点になります。
チェックリストの使い方
mentoが提供する「次世代リーダー育成進捗チェックリスト」では、以下の3つの視点から取り組みの成熟度を確認します。
- 1.次世代リーダーの選定
- 2.育成プランの整備
- 3.文化・仕組みの定着
それぞれの項目に対して、「できている」「やっているつもり」「できていない」の3段階で評価します。これにより、理想と現実のギャップが明確になり、優先して強化すべきポイントを整理できます。
チェック項目
1.「次世代リーダー」の育成候補をどう選ぶか
まずは、選定基準や候補者の特定状況を確認しましょう。
チェックリスト

2.育成プランは設計されているか
候補者に対して、どのような機会や支援を提供するかをチェックします。
チェックリスト

3.育成を支える文化・仕組みがあるか
施策が一過性で終わらず、組織に根付いているかを見ていきます。
チェックリスト

育成ギャップに応じた具体的な改善アプローチ
チェックリストで見えてきた課題に対して、どのような手を打てば改善につながるのか。ここでは、リーダー育成において特に重要な3つの観点から、具体的な強化ポイントを整理します。
1. リーダーの選定強化
「誰を育てるのか」が不明確なままでは、限られた育成リソースが分散し、思うような成果につながりません。まずは、組織として目指すリーダー像を明確にし、それに基づいた選定基準を整えることが重要です。
- 必要なリーダー像を定義し、必要なスキル・行動特性を明確化する
- 経営層・人事・現場マネージャーが連携し、現場の納得感を得られる選定フローを構築する
- 3〜5年後の経営体制を見据えて、対象人材をリストアップし、定期的に見直す仕組みをつくる
実際には、「次世代の経営者」と「部門を支える中核人材」を分けて捉え、それぞれに合った育成アプローチを行っている企業も増えています。役職や職務に応じた選定単位を設けることで、より実効性のある育成設計が可能になります。
(出典:一般社団法人日本能力協会(JMA)2023年)
2. 「育成プラン」の明確化と標準化
計画が曖昧なままだと、施策が属人的になり、再現性や効果が出にくくなります。育成プロセス全体を設計・言語化することで、現場にも展開しやすい仕組みになります。
- 育成の目的やゴールを明確にして、関係者間で共有する
- OJTやメンタリング、研修など、手法ごとにガイドラインを整備し、標準化する
- 対象者ごとの特性や課題に合わせて、柔軟に調整可能な育成ロードマップを設計する
「目的が形骸化し、施策が手段のための手段になっていた」というような状態を防ぐためにも、意図と設計の一貫性が求められます。
3. 育成文化・仕組みの定着
施策を一過性で終わらせないためには、組織全体の仕組みとして育成を定着させることが重要です。特に、育成が人事主導に留まってしまうと、現場では優先順位が下がってしまうこともあります。
- 経営層が育成の必要性と重要性を発信し、全社的な理解と納得を醸成する
- 成功事例を積極的に社内で共有し、取り組みの再現性と納得感を高める
- リーダー同士の対話の場や継続学習の仕組みをつくり、継続的な成長を後押しする
育成は“人事の仕事”ではなく、“組織の文化”へと昇華してこそ、効果が持続します。
コーチングを活用した育成事例
次世代リーダー育成において、内省を促し、意思決定力やリーダーシップの軸を磨く手段として、コーチングを取り入れる企業が増えています。
株式会社デンソーの事例:テーラーメイド型コーチングの導入
背景と課題
経営リーダー候補に対し、海外赴任などのタフアサインメントを経験させたところ、前例や過去のスキルでは対応できない状況に直面。
コーチングの活用内容
- 9ヶ月間、テーラーメイド型のコーチングを実施
- コーチが伴走しながら、意思決定の軸や自己認識を深めていく
結果と声
- 「自分の枠を超えることができ、マネジメントのスタイルが変わった」
- 「まだ見ぬ自分との出会いがあった」
- 「不安の中でもコーチの存在が支えになった」
このように、技術的な知識では乗り越えられない「適応課題」に対し、コーチングは有効な手段となります。価値観の見直しや人間関係の再構築など、マニュアルでは解決できない課題に対し個別最適な支援が可能です。
(出典:mento導入事例 株式会社デンソー)
日本たばこ産業株式会社(JT)の事例:「自立・自律」を重視した成長支援プログラム
背景と課題
次世代リーダーの早期育成を目的に、自薦制の選抜型プログラムを運用。挑戦的な業務を通じて成長機会を提供してきましたが、個々の内省や継続的な個別支援の必要性が高まり、コーチングを導入。人事部門だけでは補いきれない個別支援を、プロコーチが担う形に進化させました。
コーチングの活用内容
- コーチングは「会社がこうなってほしいと誘導するもの」ではなく、一人ひとりの内省と自律的成長のために実施
- コーチングを通じて、自分自身の考えや行動を掘り下げ、成長のきっかけを得る
- mentoの個票レポートにより、定性的な変化も可視化
結果と声
- 「コーチングは自分の棚卸しをする場。変化の実感値が大きい」
- 「受講希望者が増え、コーチングの認知度も向上」
- 「一人ひとりが自律的に選択し、学びを継続する姿勢が見えるようになった」
- 「成長支援は“全体最適”より“個別最適”を重視。自分の意思で必要な支援を選択できる仕組みへ」
この事例は、育成の主導権を個人に委ねる「自律型育成」の好例といえます。コーチングを通じた内省支援が、次世代リーダー育成における新たなスタンダードとして根づきつつあります。
(出典:mento導入事例 日本たばこ産業株式会社(JT))
まとめ
次世代リーダー育成においては、「誰を」「どう育てるか」を明確にし、組織全体でその育成を支える体制づくりが求められます。
- 自社の育成状況を見える化する
- 選定・育成・定着の各フェーズでギャップを明確化する
- コーチングなど個別最適化された支援と、組織的な仕組化を両立させる
育成は短期で成果が出る取り組みではありません。しかし、戦略的に進めることで、次世代の経営を担う人材を着実に育てることができます。人事担当者として、まずは現状を可視化し、自社に合った育成戦略を描いていきましょう。