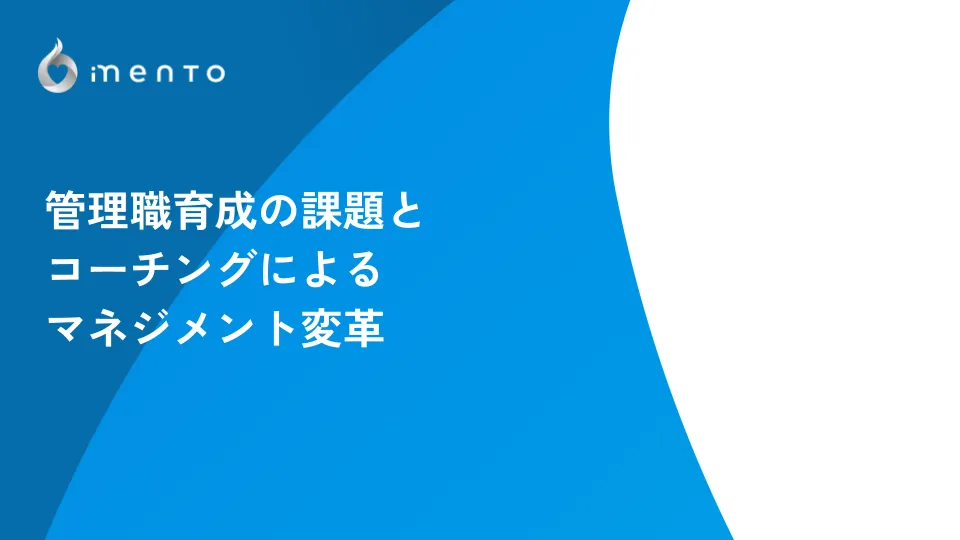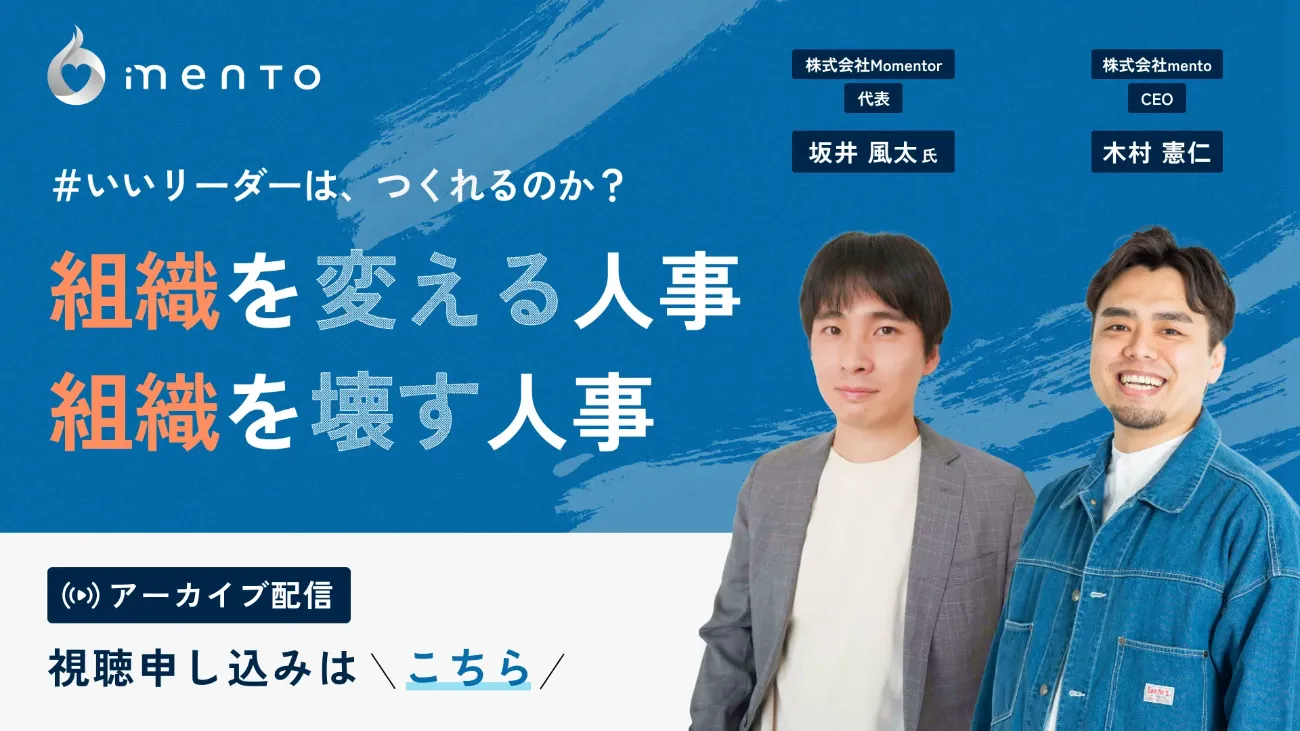経理部 次長 村上弘樹さん
「圧」を消すのではなく、使い分ける──45歳管理職がコーチングで組織エンゲージメント向上を実現した自己変革プロセス
INDEX
「これまで自分自身努力の積み重ねで成果を出してきたから、人が育つには努力を重ねてもらうことが大事だと思っていました」──日本たばこ産業(JT)で工場から総務、事業企画まで様々な部署を経験し、37歳で管理職となり、45歳でコーチングを受け始めた村上弘樹氏。
専門性の高いファイナンス領域で人財育成・キャリア構築等の人財課題に直面するとともに、自分自身のマネジメント能力の向上のため、コーチングを導入。自身がこれまで無意識にかけていた「圧」の存在に気づき、それを「消す」のではなく「使い分ける」重要性を学びました。メンバーのより一層の自主的な行動や組織エンゲージメントサーベイの向上という具体的な手ごたえとともに、マネジャーとして変化した彼の軌跡を追います。
複数の部署を経たから見えた、ファイナンス人財育成の課題

まず、村上さんの現在のお仕事と、これまでのキャリアについて教えてください。
村上:2003年にJTに新卒で入社し、今年で22年目を迎えます。メーカーなので当時は営業現場か工場でのキャリアスタートが一般的で、私は工場での生産管理・品質管理の仕事からキャリアをスタートしました。
そこから本社製造部の原価チームへ異動し、数字を扱う仕事に就いたあと、公募制度で総務部に手を挙げました。一般的な企業でイメージされる「総務」とは少々異なり、私は行政対応や渉外活動を担当していました。その後、JT株の売却プロジェクトを経て、久々にたばこ事業へ戻って事業企画、工場の現場でのマネジメント、加熱式たばこの日本窓口など、様々な経験を積むことができました。
2017年から管理職となり、子会社出向なども経て、現在は経理部に籍を置きながらファイナンス分野のHRBP(HRビジネスパートナー)として働いています。コーポレートに所属する経理、財務、税務に加え、たばこ事業内に配置されるファイナンス領域の人財配置や成長支援を担当しています。
現在のHRBPの仕事について、ミッションなども教えてください。
村上:経理や財務、税務室といった、いわゆる「経営ファイナンス分野」に属する人財はJTグループ内に約300人いて、様々な部署に散らばっています。この方々の成長を支援し、いかに配置し、業務で役割を発揮していただくか。メンバー一人ひとりが自立・自律したキャリアパスを描いていくことをサポートしていくか。そして、組織開発を通じて成果の創出につなげていくか。言わば、人事部に近い領域の仕事でもあります。
──ありがとうございます。管理職に就かれてから8年経ちましたが、コーチングを導入しようと思われたきっかけは何だったのでしょうか?
村上:組織的な課題と個人的な課題、両方ですね。
組織的には、マネジメント層の成長支援ではファイナンス領域の専門性の高さが課題となるのではと思っていました。私のように複数の部署を経験しながら人を育てることは難しく、機能が本社に集約されているため、現場経験も積みにくい。現場では専門性ではなく、人間性で勝負するしかないので、多様な人を巻き込むマネジメント力が身につきますが、ファイナンス領域で専門性を高めるなかではそういった機会が少ないという現状があります。
個人的な課題では、人を育てる難しさに直面していました。37歳で管理職になり、それまでは自分なりに努力して成果を上げ、昇進してきた自負がありました。正直に言えば、「人が育つには努力が大事」だと本当に思っていたんです。でも、現場でマネジメントをしてみると、自分が経験してきたことと、実際に人を育てることの乖離に悩みました。また、マネジメントは非常に孤独です。上司に相談したいことがあっても、「これを相談したら自分の評価が下がるのでは」といった葛藤もあってなかなか相談ができませんでした。
「マネジメント層を育成するためにコーチングは有効なのか」という組織目線での検証と、「自分のマネジメントスタイルが正しいのか」という個人的な葛藤から、まずは自らコーチングを受け始めました。
「自分のトリセツ」作りで気付いた、無意識の「圧」のチカラ

コーチングを始めた当初はいかがでしたか。
村上:正直、最初の1ヶ月は「自分は何をしているのか?」という感じでした。何をアウトプットしているのか、悩み相談をしているのか、よくわからない状態で進んでいました。
転機になったのは、コーチから「村上さんの特性を一度掘り下げて、“自分のトリセツ(取扱説明書)”を作りましょう」と提案されたことです。
「自分のトリセツ」を作る中で、どのような気づきがありましたか。
村上:「圧」にフォーカスできたのが大きな気づきでした。私は学生時代から野球や陸上競技といったスポーツを続けてきて、県大会優勝や全国大会出場といった経験を積めたんです。その一種の成功体験は仕事でも同様につながっていて、どこかで「やればできるし、成果につながる」という実感を持って成長してきたんです。
その成長の原動力は、自分に「圧」をかけることでした。プレッシャーを自分にかけて、それを乗り越えることで成果を出してきた。これが自分の特性だったんです。
メンバー時代は「圧」を自分に向けることで成長できていても、マネジメントになるとそれが部下へ向かってしまう。「なぜできないんだ」「なぜやらないんだ」と思ってしまうような衝突がありました。
その「圧」について、コーチとどのような話をしたのですか。
村上:最初は「圧を消した方がいいのでは」と考えたんです。マネジャーとして「圧」を持っているのは良くないと。でも、自分のアイデンティティを考えるセッションの中で、コーチから「本当にそれを捨ててしまっていいんですか」と問われました。
そこで気づいたのは、「圧」は消すのではなく、あくまで使い方が大事だということです。「圧」を持っているという自覚を持った上で、ここでは出さない方がいいのか、むしろ出した方がいいのか、相手や状況によって使い分けるということです。
そういった視点を持てるようになったのは、本当に大きな学びでした。
他部署との比較を手放し、メンバーに任せるマネジメントへ

コーチングを通じて、マネジメントスタイルはどのように変わりましたか。
村上:大きく2つの変化がありました。一つは、他チームとの比較を手放せたことです。私のチームはJT全体の業務から言えば専門性を発揮して組織貢献を果たすといった業務ではない総務的な仕事が多く、評価者会議で他のチームよりも評価されないことがありました。「他のチームでこんな成果を上げたや、メンバーがこういったPJに携わった」などと聞くと、コンプレックスや悔しさを覚えていたんです。
でも、コーチングで「なぜそれにこだわるんですか」「それは捨ててはいけないのですか」という問いを投げかけられ、「確かに比較する必要はない」と気づきました。我々は我々で、課せられたミッションにどれだけ向き合えるかが大事だと。
もう一つは、メンバーに任せるようになったことです。成果に固執しすぎず、「まずはやりたいようにやってみて」と言うことが多くなりました。
つい最近も、メンバーに成長支援の課題整理を2ヶ月前に頼んでいたのですが、あえて進捗を聞かずにいました。昔なら「できているのか」「いつまでにやるんだ」と逐一聞いていたでしょうが、今は「最後は自分がリカバリーすればいい」くらいの気持ちでいられます。
まさに、メンバーに任せることでの中長期的な人材育成と短期的な成果のバランスは難しいと思いますが、どのように考えていますか。
村上:短期的に自分が成果をあげるのは簡単ですが、チームの力になりません。自分が手を出すことが多くなると、結局メンバーは成長しないし、また同じことを繰り返します。こらえて我慢してやってもらって、良かった点は良かったと言うし、改善点があれば「もうちょっとこうした方がいいよね」という言い方に変えています。「できていない」ではなく「もうちょっとこうした方がいい」。この言い方の違いは大きいと思います。
成果を上げることだけが全てではないし、人を育成するというのは、すごくおこがましいことだと感じるようになりました。実際は育成の手伝いをするくらいしかできない。メンバーにとって「村上と一緒に仕事をしたことが印象に残ることができればいいな」くらいの気持ちに変わりました。肩の荷が下りた感じで、結果として自分も気楽になり、そしてそのほうがいいチームや成果につながると実感しています。
エンゲージメントサーベイで見えた具体的な組織の変化

村上さんが変わったことで、チームの変化を実感することもありますか?
村上:エンゲージメントサーベイを3ヶ月に一度実施しているのですが、明らかにスコアが向上しています。特に「支援」や「人間関係」といった項目で高いポイントが出るようになりました。
私がコーチングを始めたのが2024年2月頃で、それ以降、上昇傾向にあります。これまで上がったり下がったりを繰り返していたのですが、とても良い方向へ進んでいますね。
メンバーからの直接的な反応はいかがですか。
村上:コーチングを受けていることもオープンにしているので、「少し柔らかくなりましたね」と直接言われることもあります。
印象的だったのは、お休みされていた方が復帰された時にかけられた言葉です。1年半ほど休まれていたのですが、「だいぶ変わりましたね、このチーム。一人ひとりが自分のやることを理解して、自発的に動き始めて、チームっぽくなりましたね」と。これは本当に嬉しかったです。
チームメンバーとの仕事の進め方も変わりましたか?
村上:情報共有は、これまで以上にオープンにしています。エンゲージメントサーベイの結果も全部見せますし、「僕はこう思うけれど、皆さんはどう思いますか」と問うスタイルで進めています。メンバー間の情報格差はつけたくないし、絶対にしません。機密性の高い案件は別としても、基本的には差をつけないことを大切にしています。
マネジメントの孤独を支える、社外コーチの価値

改めて、マネジャーがコーチングを受ける価値をどう捉えていますか。
村上:マネジャーは本当に孤独です。横の同僚にも相談しづらいし、上司にも「自分の弱みを見せているのでは」「評価が下がるのでは」という葛藤があります。どうしても利害関係が出てしまうんです。
そこに対して外部にコーチがいて、悩み相談ではないけれど、「何が起きているのか」を話した中で壁打ちをしてもらいながら、「ここはこうした方がいいよね」「こういう風に次はやってみよう」と素直に話しあえる。このやり取り自体に、すごく価値があります。
社外に相談相手を持つことの意味は大きいですね。
村上:社外のネットワーキングで相談相手を作ることもできますが、それも結局は「他人事」として返ってくることが多いと思います。コーチの場合は、対等な話ができるというのが大きな価値です。本当に救われました。
また、自分を客観視できることも重要です。社内には客観視できる仕組みはなかなか無いものです。360度サーベイなどもありますが……やはり、どこか建前の部分も出てきますし、批判的なコメントを見てマネジャーは顔が暗くなるものです。でも、「なぜ、そういった結果になるのか」を客観的な目線で一緒に考えてもらえるコーチがいれば、マネジメント力を上げていく上で重要なツールにもなり得るはずだと思っています。
「圧を消すのではなく、使いこなす」という話もしましたが、批判をただ受け止めるだけでは、オール・オア・ナッシングの世界になってしまいます。良さを消してしまうし、人格まで否定されているような気分になってしまう。コーチと一緒に、一つひとつを紐解いてやっていくのが、具体的なハウツーとしてあるのではないでしょうか。
10年後の役職定年を見据えた、ファイナンス人財育成への想い
今後の村上さん自身の展望についても聞かせてください。
村上:私は45歳ですが、今はこれまで育ててもらった会社にどう貢献し、還元していくか何を残せるのか、恩返しできるのかというステージにに来ています。
ファイナンスHRBPを立ち上げたのが私なので、まずは軌道に乗せたいと思っています。ファイナンスは企業の根幹をなすファンクションですが、会社の運営体制が大きく変わり、ファイナンス人財を体系だって育成していく仕組みを1から作っていく必要が出てきました。親会社として、ホールディングスとして、ファイナンス人財をどうしていくかという仕組みを構築し、それが継続的に運用できる体制までもっていきたいです。
また個人的には、人生100年時代と言われる中、セカンドキャリアについても考える歳になりました。人事系の仕事もキャリアのオプションの1つになるかなと考えています。これまでのキャリアを振り返ると「何屋さんかよくわからない」のですが(笑)、最後は「人事屋でもあります」と言えるようになりたいですね。
チームとしてはどのような方向を目指していますか。
村上:今まではファイナンスの総務的なところを主軸にやってきましたが、HRBPとして専門性を発揮できるような仕事に、より力を入れていきたいです。そのためにはもう少しだけ組織の強化が必要だと思っています。会社からもそう評価され、強化していこうといってもらえるように、チーム一丸となり、みんなで頑張っていきます。