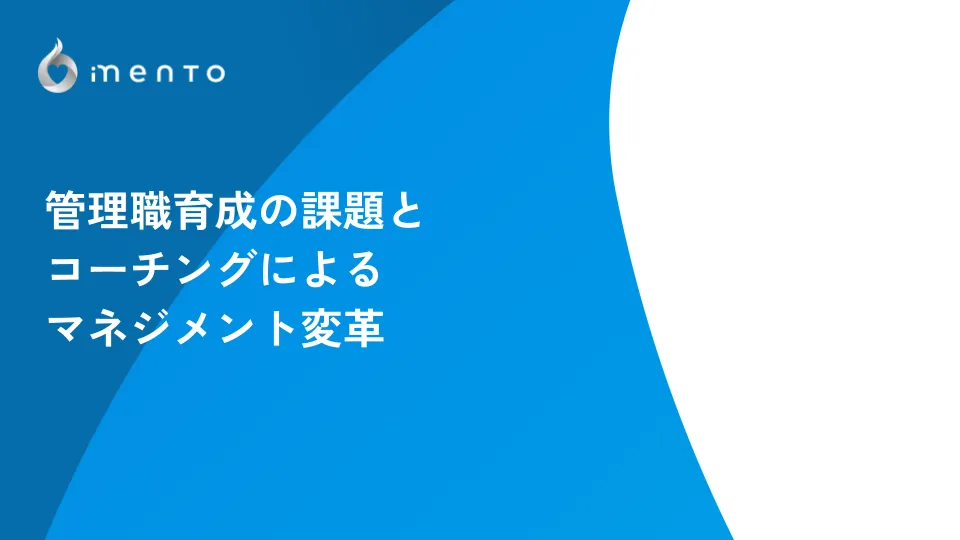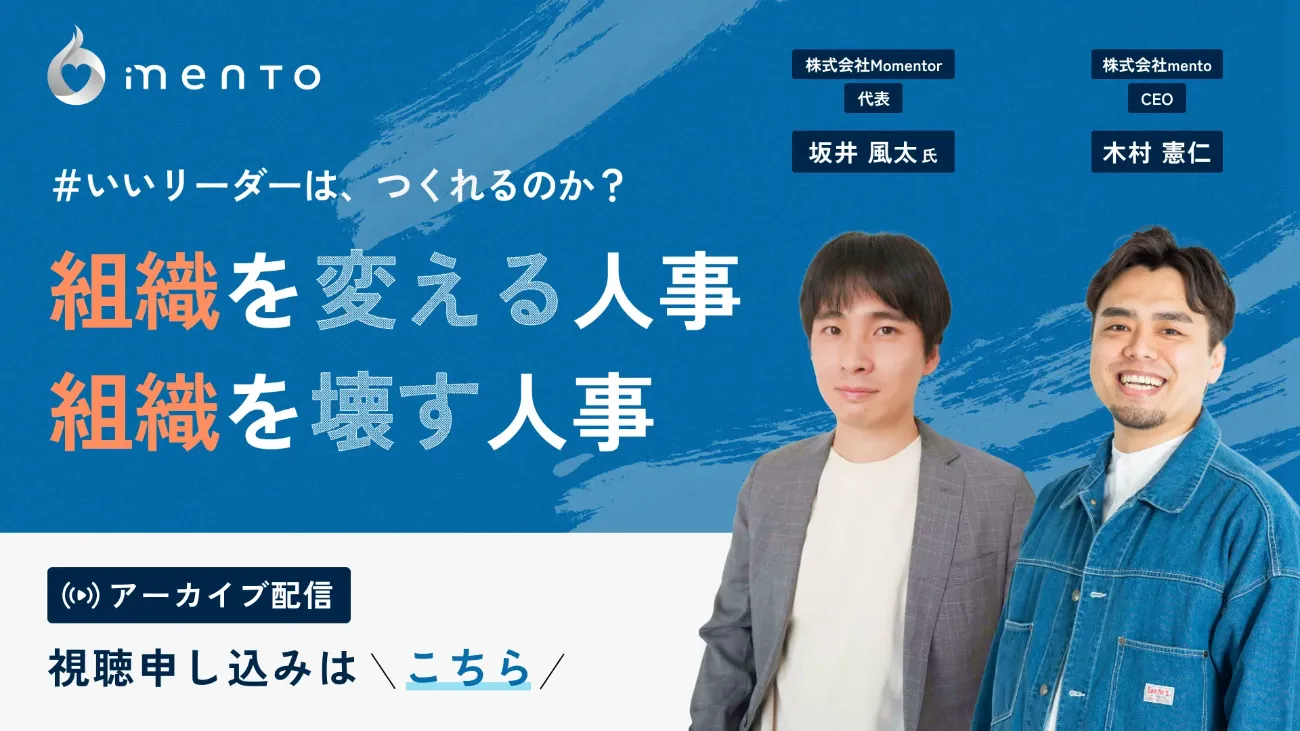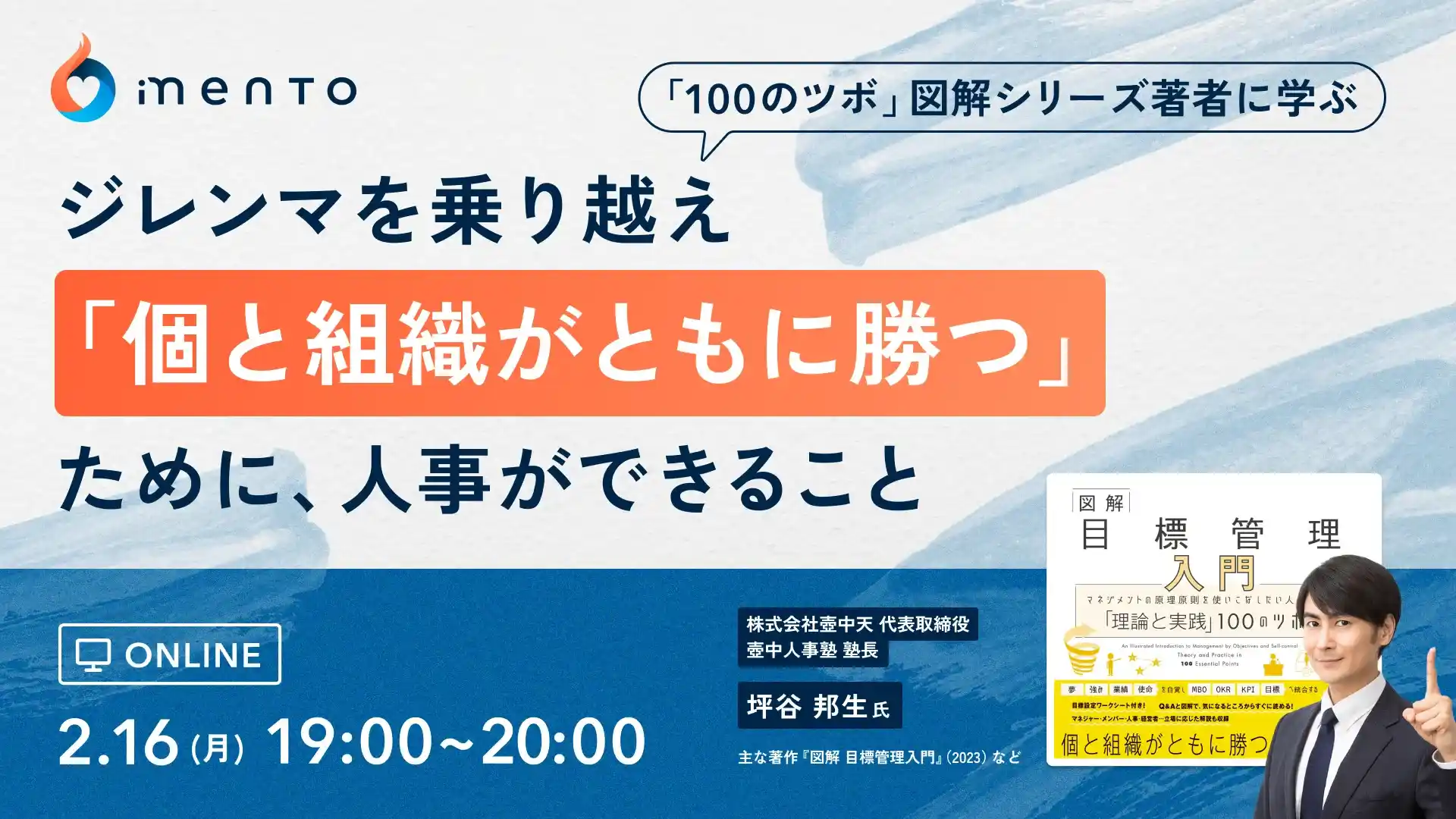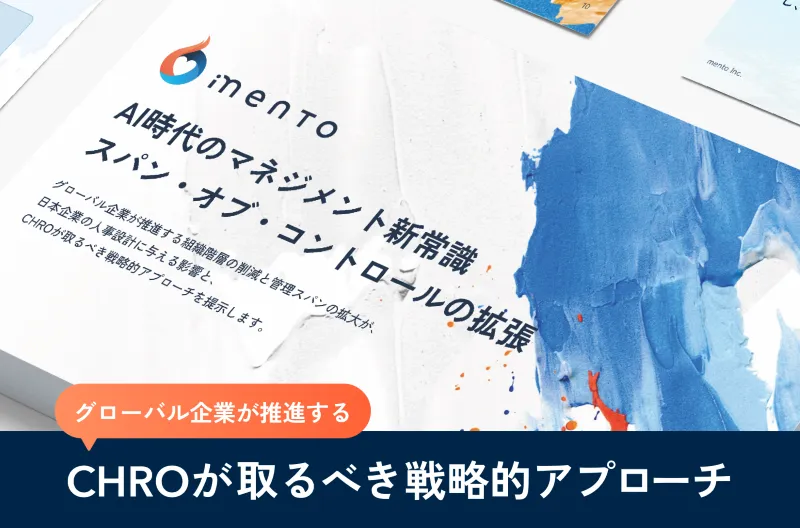株式会社ユーザベース 執行役員 スピーダ事業 通信領域アカウント統括 吉田佑弥さん
mento登録コーチ/株式会社メルカリ AI推進室マネージャー 浅井宗裕さん
3年間のエグゼクティブコーチングで変わったこと、そして「AI時代のリーダーシップ」を考える
INDEX
AI全盛期において、経営戦略の仕事はどう変化するのか。そして、不確実性が増す時代に、リーダーはいかにして成長し続けるべきなのか──。
ユーザベースで通信領域の事業統括を務める吉田佑弥氏は、3年間にわたってコーチングを継続受講。「個人の成果」から「チームマネジメント」、そして「社会・産業へのインパクト」まで段階的に視座を上げてきました。AI時代における人間の役割と、コーチングの本質的価値について、担当コーチの浅井宗裕氏とともに語り合いました。
プロフィール
吉田佑弥(よしだ ゆうや) 株式会社ユーザベース 執行役員 スピーダ事業 通信領域アカウント統括。2010年サイバーエージェント入社後、インターネット広告コンサルタントとして従事。教育系ITスタートアップでの法人事業立ち上げを経て、2020年3月にユーザベースに入社。現在は通信キャリア向けエンタープライズセールス組織を統括し、経営戦略から営業戦略まで幅広い領域でソリューション提供を行う。2022年からコーチングを継続受講中。
浅井宗裕(あさい むねひろ) mento登録コーチ/株式会社メルカリ 経営戦略室 AI推進マネージャー。2019年からコーチングを始め、累計2000時間以上のビジネスコーチングを提供。経営戦略・AI推進の実務と並行して、ビジネスパーソンの成長支援に携わる。
AI時代でも変わらない、人間だけが担える2つの役割

浅井:吉田さんは経営戦略に関わる事業をリードされていますが、生成AIの進化で「もうコンサルはいらないのでは」なんて声も聞こえるようになってきました。経営戦略の仕事は全てAIに取って代わられるのか、それとも人間が果たすべき領域があるのか。どうお考えですか?
吉田:今のご質問を私なりに言い換えると、知的生産性を求められる人間の「役割」の変化とは何か、だと思います。その上で、やはりAIはあくまで“HOW”の一つでしょう。人間にしかできない役割があると考えます。
役割の一つ目は意思決定です。AIが高度な予測を行えるようになっても、正解のない世界で勇気を持ってジャッジし、その結果に責任を負うことは人間にしかできません。AIはあくまで、従来よりも広く深い情報を提供する存在であり、意思決定の精度を高めたり、多様な選択肢の中から覚悟を決める勇気を後押ししてくれる存在だと捉えています。
もう一つの役割は、人間同士の信頼関係の構築です。チームを作って何か大きなことを成し遂げる構造は、今も基本的には変わっていません。現場でしか生まれない空気感や相互の信頼は、やはり人間にしかできない築けないものだと思います。
AIがチームビルディングの秘訣を教えてくれたり、チームの状態が良くないときに客観的なアドバイスをしてくれることはあっても、最後にそれを実行するのは人間です。この領域の重要性は、今後さらに高まっていくのではないでしょうか。
浅井:私も今のところ、AIは「1%から99%」を得意とする存在だと捉えています。最初と最後の1%、「0%から1%」「99%から100%」は、人間の役割ではないでしょうか。
吉田:まさにそうですね。判断の根拠となる情報の精度が上がるだけで、判断や意思決定をする行為自体ははるか昔から変わっていません。そもそも新聞やインターネットの登場で情報アクセスは飛躍的に向上しましたが、意思決定の構造自体は同じでしたから。

コーチングがもたらした、劇的な「自己認識の向上」
浅井:そんな時代の流れの中で、吉田さんは3年間継続してコーチングを受講されていますね。最初はどういったきっかけがあったのですか?
吉田:ユーザベース社内で、コーチングがリーダーシップに大きな影響を与えるのではないか、という仮説が上がったんです。実際に受けてみると様々な変化がありましたが、一言で表現するなら自己認識が圧倒的に向上しました。まだまだ不十分だとは思いますが、過去の自分と比較すると大きな変化です。
最も大きな気づきは、仕事でもプライベートでも、すべては自分の特性を正しく理解し、受け止めるところから始まるということです。弱さや苦手な部分も含めて、自分をありのままに受容する。それができるようになると、いざ前に進みたいときに、以前なら不本意な選択をしてしまっていた場面でも、勇気を持って別の一手を選んだり、違う発言やふるまいができるようになりました。
その変化のおかげで、リーダーシップの発揮の仕方も大きく変わってきた実感がありますし、キャリア形成にも確実に影響しています。特に、自分自身がキャリアを見直したり、新たな一歩を踏み出そうとするときには、浅井さんに視座を引き上げてもらっている感覚があります。
浅井:それは嬉しいです。
吉田:浅井さんからいただいたフィードバックで特に印象に残っているのが、「吉田さんの発言は成果に強くコミットしている一方で、コントロール可能な領域に固執しているように聞こえる」という言葉です。目標は何としてもやり遂げたい、一方でやり遂げないと自分が周りからディスカウントされていると感じてしまう――そんな不安と戦っていることを見事に言い当てられたと感じました。
その不安があったからこそ近視眼的になりがちで、人をコントロールしようともしてしまう。そのフィードバックを受けてから、自分の内面に少しずつ変化が生まれたことを、今でもはっきりと覚えています。
浅井:改めてどのような悩みや葛藤だったんでしょうか?

吉田:お恥ずかしい話ではありますが、他者からの承認に依存したり、うまくいっていないときに自己効力感が下がって不安になったりすることがありました。その防衛反応として、メンバーに感情的になってしまったり。「なぜできないんだ、もっとできるはずだろう」とコミットメントという名目で強く当たることや、上司へ一方的に反発するようなこともありました。要は「対話」ができていなかったんです。
怒りたいわけではないんです。もっとうまくやりたいし、成果を出したい。「なぜ、こうなってしまうんだろう……」と悩んでいたとき、浅井さんは私の不安や恐れの根っこにある要因を、とても丁寧に紐解いてくださいました。
この紐解きは1回や2回では終わらず、1年、2年と継続的に向き合ってきました。興味深いのは認識してもまた異なる自分が現れたり、分かっていたはずなのに同じパターンに陥ってしまったりすること。行ったり来たりを繰り返しながらも、徐々に揺らぎが少なくなっている実感があります。今でも正直揺らぎはありますが、いよいよ「これが自分なのだ」と受け入れられるようになってきました。浅井さんの言葉で言えば、「内包する」という感覚に近いと思います。
もともと「コントロールしたい」という性質があるので、不確実な状況はできるだけ避けたい。でもその一方で、不確実なことにこそ挑戦したいという矛盾も抱えている。そんなとき浅井さんから「吉田さん、それは“内包する”んですよ」と言われて、確かにその通りだと感じました。
たとえどこか気持ち悪くても、それでいい。浅井さんが言った「気持ち悪いものを内包する胆力こそが、リーダーの器じゃないですか」という言葉には、とても納得させられました。
浅井:そうした変化は、吉田さん自身が「変わりたい」という意志を明確に持ち、悩みながらも変化そのものに真摯に向き合い、コミットしていたからこそ生まれたのだと思います。
吉田:実は過去3年間のコーチングセッション27回分の議事録をAIに読み込ませて、変化を分析してもらったんです。結果は明確で、2022年は個人の成果と短期的な目標達成にフォーカスしていましたが、2023年はチームマネジメントやリーダーシップ、2024年は社会や産業全体へのインパクトへと視座が向上していました。
浅井:興味深い分析ですね!
AI時代におけるコーチングの独自価値

浅井:先程の経営戦略の話と同じく、コーチングにおけるフィードバックコメントの99%くらいはAIで担えるようになるかもしれません。ただ、やはり「最後の1%」とか、セッション後の「とにかく楽しかった!」とかいった感覚は、まだ人間同士に残されていると思うんです。コーチングを受ける上で人とAIではどこに違いがあると考えますか?
吉田:事実として、AIでコーチング的な壁打ちもできますし、それを否定するつもりは全くありません。好みの問題もあるでしょう。ただ、特に浅井さんというコーチに関して言えば、私には明確に「浅井さんでなければいけない理由」があります。
まず最も大きいのは「信頼」です。「誰に言われたか」ということは、自分を奮い立たせたり、エンパワーしたりする観点で極めて重要です。浅井さんは時に率直な言葉も交えつつ、新たな気づきを与えてくれます。同じ内容をAIに言われたとして理解はできても、納得や腹落ちのレベルは違うと思います。さらに、複雑な感情の読み取りや洞察も、現時点でのAIには難しい領域です。浅井さんは様々な文脈を複合的に読み取って、経験や感性を交えながらフィードバックしてくれていますから。
あと私の場合はコミットメントも引き出されると感じています。浅井さんとの定期的なセッションの中で、「次回までに何かアップデートしていたい!」と思うんです。必ずしも前進せずとも、何かにトライして、約束したことを持参できるようにしています。これもコーチングの相手が「人」である関係性だからこそではないでしょうか。
浅井:確かに、吉田さんはコーチングセッションの最後に必ず宣言や約束をしてくださいますね。次のセッションはその振り返りから始まる。そもそも吉田さんの頭の中にない問いは、吉田さんからもAIからも出てこない。それを私が問いとして投げかけることで、何らかの化学反応が起きるということもありそうです。

吉田:おっしゃる通りかもしれません。技術進化によってAIコーチングの品質が人間のコーチングを上回る可能性だってありますが、人と向き合って対話をするという体験自体はなくならないはずです。恋人や家族、友人と対話するときも、答えを求めているわけではない。むしろ、対話を通じて共感してもらい、感情を受け止めてもらい、時には痛いところを突かれてハッとする。そうした瞬間があるから「もう少し頑張ろう」と思える。それは人間同士だからこその価値でしょう。
何度も“Why”に立ち返り「勇気ある意思決定」をする
浅井:正解のない世界で、勇気を持って意思決定することは人間にしかできないという話もありましたが、コーチングを通じて吉田さん自身が意思決定されたことについてもお聞かせください。
吉田:印象的だったのは、2022年10月から12月のシーズンにした意思決定ですね。当時、未経験だったエンタープライズ領域にチャレンジすることで、自分のキャリアを大きく変えようと決断したんです。そのときに、浅井さんから背中を押していただいたことを覚えています。
あとは、AIの進化についてワクワクしながら浅井さんに話していた際に、自分でもそこまで気づいていなかったんですが、「吉田さんは、これからの時代においてユーザベースにとどまらず、社会全体のAIシフトを促していくようなステージに来ているんじゃないですか」と言われたんです。
そのフィードバックをきっかけとして、今そうなれているかはおいておいても「そうなりたい」と明確に思えるようになりました。少しずつ社内における発言の機会も増え、信頼もあとから追いついてきたと思います。

浅井:人が腹を決められるかどうかって、結局のところ立ち返るべき“Why”を煎じ詰められるかどうかだと思うんです。「これさえ叶っていれば後悔しない」とか、「不可逆でないなら、やってみるしかない」とか。この“Why”を突き詰める作業が、私と吉田さんの間で機能したからこそ、意思決定を後押しできたのかもしれません。
吉田:“Why”を突き詰めることは、不確実な時代において特に大切ですよね。たとえば、自分は何をしたときにワクワクするか。動機を言語化するところから始めることが多いですね。
一方で、これは先ほどの話にも通じますが、「これが正解だ」と最後まで思えない気持ち悪さや不安を受け止めることも必要です。無理にポジティブになる必要もないし、明るくふるまう必要もない。「しんどいし、どうなるかわからない」と言いつつも、どこかで「とはいえ大丈夫だから」とも思える。なぜなら、「成果が出る時」と「頑張っている時」は、どうせ時期がずれるからです。
そうして、肩の力がすっと抜けるような瞬間を保ちながら、時には気合いも必要だけれども、続けていく。そういうバランスを個人的には大切にしています。
浅井:「今、置かれている状況」に飲み込まれず、課題から距離を置いてメタ認知すること。その上で「なぜ自分はそう思うのか、本当はどうしたいのか」を問うことは本当に大切ですよね。それをAIに問うことも有効かもしれないし、コーチと色々話して一緒に整理するのも有効かもしれません。
AI時代にユーザベースが成し遂げる未来
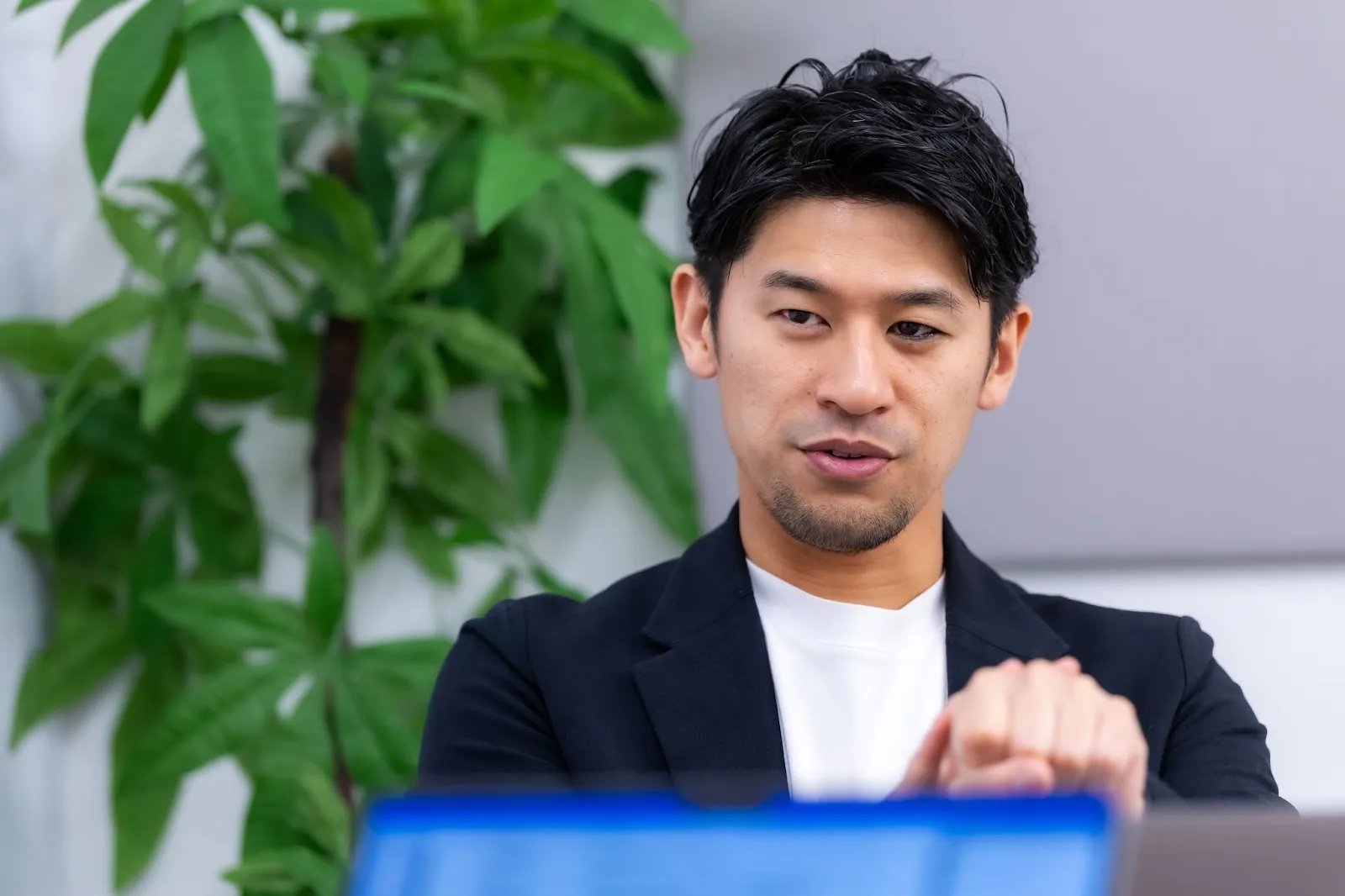
浅井:個人の成果からチーム、そして社会へのインパクトへと視座を上げてきたという話もありましたが、このAI時代の社会に対してユーザベースではどのような未来を作ろうと考えているんですか?
吉田:AI時代における我々の存在価値は明確です。まず最も重要なのがデータ。「データは新しい石油」と言われますが、各ニュース媒体がLLMにデータを食わせることを拒んでいるように、LLMに食わせられるデータの質が限定されていると、アウトプットが陳腐化してしまいます。その中で、ユーザベースが17年間かけて育んできたデータの優位性が増すと考えています。具体的には、信頼性の高いアナリストのデータや業界レポート、あらゆる産業の企業情報を構造化した財務データ。さらに「NewsPicks」のメディアを持っていることもデータにおける優位性になると考えています。NewsPicksには編集部の独自記事と、プロピッカーたちのスタンスを取った「私はこう思う」というコメント、そして24万人以上のエキスパートネットワークがあります。これらを統合的にLLM技術に活用することで、我々にしか出せない深いインサイトを提供できると考えています。
もう一つがUI/UXです。AI時代において相対的にUIの価値は下がり、AIエージェントが色々な情報を取りに行って答えを出すとも言われています。一方で、AIは魔法の杖ではないので、何万人の組織では特定の課題解決をするときに自由度の高いプロンプトは使われないと思います。たとえば、営業の領域でAIを渡されて自由に使っていいよと言われるのと、我々のアプリケーションで「顧客向け提案資料作成」ボタンを押すだけで、信頼できるデータと最適化されたプロンプトをもとに3C分析から直近の決算情報、提案ストーリーまでが整理されてアウトプットされるといった体験は圧倒的に違うでしょう。
これらデータフィードビジネスとアプリケーションによる課題解決の両面で事業を展開していきます。
浅井:経営戦略とAIが掛け合わさる領域をユーザベースが切り拓いていく面白さが伝わってきました。最後に、コーチングをユーザベース社員にも勧めるとしたら、どういった人に受けてもらえると効果的だと思われますか。
吉田:何よりもコーチングを受ける側のスタンスが重要です。自分自身が現状を脱して変わりたい、アップデートしたいと心から思っている人ですね。やはり、フィードバックを受けるときって、どんなに優しい言葉や表現だったとしても「痛み」を感じることがある。それを受け止められるかどうかが非常に大切です。

mentoインサイドセールス祐川・広報岩田とともに